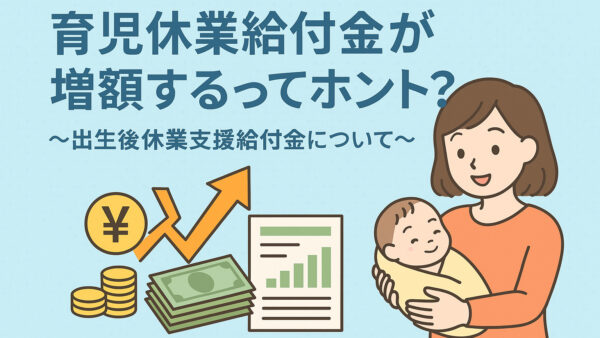最終更新:2026年2月11日
出産したら役所に提出する書類は全部で6つあります。
出生届、児童手当、扶養届、出生通知書、乳幼児医療費助成、018サポート(東京都)。それぞれ提出期限や必要なものが異なるため、事前に把握しておくことが大切です。
社労士法人Aokiが、男性育休取得の実体験も交えながら、出産後の提出書類について期限・提出先・必要なものを分かりやすくまとめました。
この記事が皆様の一助となれば幸いです。それでは早速みていきましょう!
子供が生まれたらやる手続き一覧|届出6つ
- ①出生届|必要なもの・提出先・期限
- ②出生通知書|出生届との違い
- ③扶養届|会社への届出と必要書類
- ④児童手当|申請期限と必要なもの/a>
- ⑤乳幼児医療費助成|マル乳医療証の申請方法
- ⑥018サポート|月5,000円の申請方法(東京都)
①出生届|必要なもの・提出先・期限

☆子どもが産まれたことを伝える届出です。
まずはこれが最優先!
【期限】
- 産まれてから14日以内
→お子様の氏名の記載が必要ですので、14日以内に名前を確定しましょう。
【提出先】
- 子の出生地・本籍地又は届出人の所在地の市役所,区役所又は町村役場
→私は東京都在住で、妻の里帰り出産で大阪で届出しましたが問題なく通りました。
【必要なもの】
- 出生届、出生証明書(医師または助産師が作成したもの。出産した病院が発行してくれます)
- 母子健康手帳
- 本人確認書類(運転免許やマイナンバーカード)
- 印鑑(任意になりましたが、あると安心)
– 参照 法務省「出生届」
②出生通知書|出生届との違い

☆各自治体がこんにちは赤ちゃん訪問や育児サービスなどの対象者や住所を把握するための届出です。
出生届とごっちゃになりやすいのでご注意を!
東京都ではこんにちは赤ちゃん訪問を受けることで、10万円相当のカタログギフトをもらえるので忘れずに!
【期限】
- 産まれてから14日以内
【提出先】
- お住まいの市区町村の保健所や保健センター
【必要なもの】
- 特になし 電子申請で提出するのがオススメです!
– 参照 厚生労働省 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の概要
③扶養届|会社への届出と必要書類

☆これは会社に依頼すれば、手続きをしてくれるケースがほとんどだと思います。
後述する手続きなどにお子様の保険証が必要となることが多いので、会社への連絡を忘れずに!
【期限】
- 出生後、なるべく早めに
【提出先】
- 会社(もしくは健康保険協会か健康保険組合)
【必要なもの】
- お子様のマイナンバーか住民票
(マイナンバーの通知カードは出生届を提出後、3週間ほどかかるので住民票の添付が早いですね。)
– 参照 全国健康保険協会 被扶養者とは?
④児童手当|申請期限と必要なもの

☆月額で手当がもらえる申請です。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなるので、こちらもお早めに!
【期限】
- 出生の翌日から15日以内
【提出先】
- 現住所の市区町村(里帰り出産の場合でも、現住所への申請となるので注意!)
→こちらも電子申請がオススメです。
【必要なもの】
- マイナンバーカード(保護者)
- 申請者(赤ちゃん)の保険証の写し
- 手当の振込先の銀行口座情報
※各市町村によって必要なものが多少異なるので、事前に確認を!
– 参照 こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
⑤乳幼児医療費助成|マル乳医療証の申請方法

☆国民健康保険や健康保険の自己負担分を助成してくれる制度です。
【提出先】
- お住まいの市区町村
【助成方法】
- 病院などで保険証を提示する際に、マル乳医療証を提示します。
【必要なもの】
- 乳幼児の健康保険証の写し
- 保護者と配偶者のマイナンバーの分かるもの
- 保護者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)
– 参照 こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」
⑥018サポート|月5,000円の申請方法(東京都)

☆都内に在住する18歳以下の子どもに対し、1人あたり月額5,000円の支給が受けられます。
【提出先】
- 東京都(電子申請が便利です)
【必要なもの】
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 申請者と子どもの家族関係を確認できる書類(保険証や住民票など)
- 振込口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード)
– 参照 東京都 018サポート 公式サイト
まずはざっくりこのあたりでしょうか。
各自治体によって必要な書類などが異なる場合もありますので、事前に確認をとっておくと、より安心ですね!
📚 出産・育休に関する関連情報
出産後の手続きが一段落したら、育児休業中の給付金や働き方についても確認しておきましょう。
出産後の手続きが一段落したら、育児休業中の給付金や働き方についても確認しておきましょう。
→ 2025年からの新制度で、育休中の収入がどう変わるか詳しく解説しています。
→ パパ育休中に少し働きたい場合の注意点。社会保険と雇用保険で扱いが違うので要チェックです。
社会保険労務士法人AOKIでは、企業の育休取得推進から各種手続き代行まで、トータルでサポートいたします。お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。